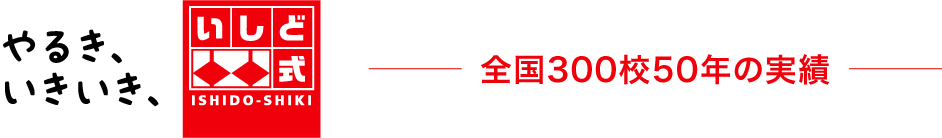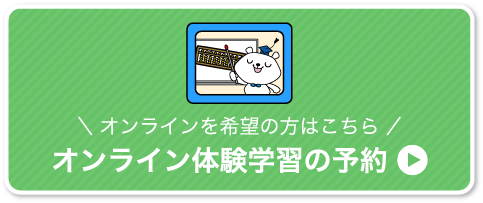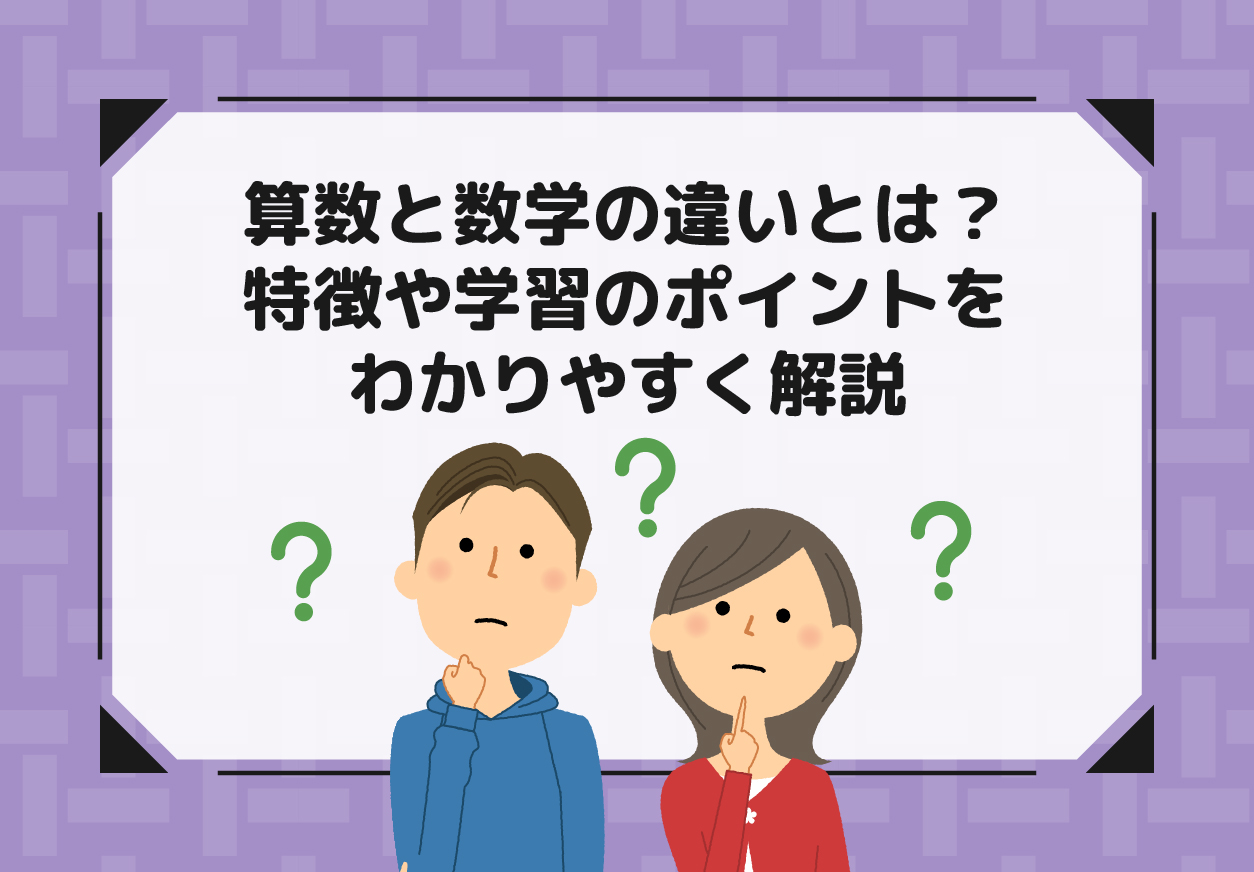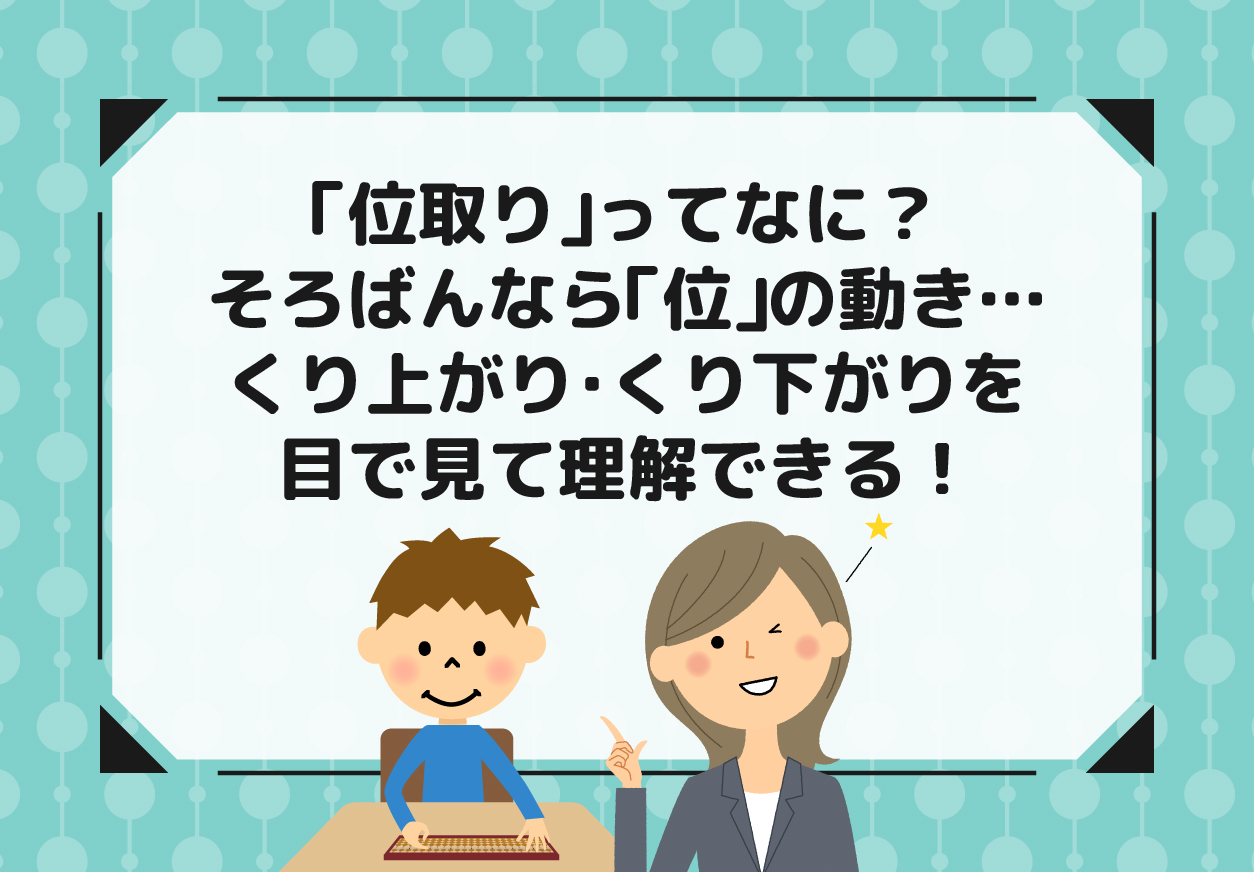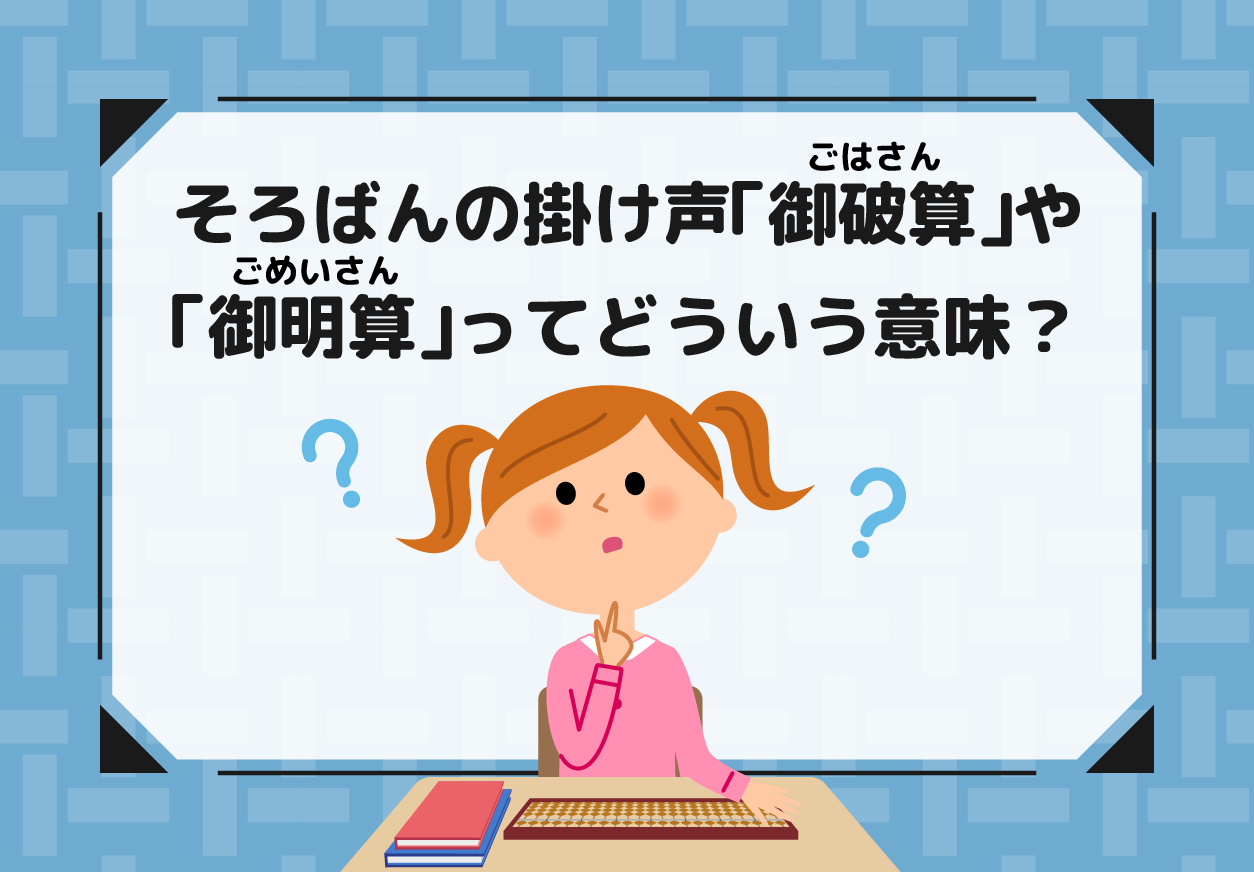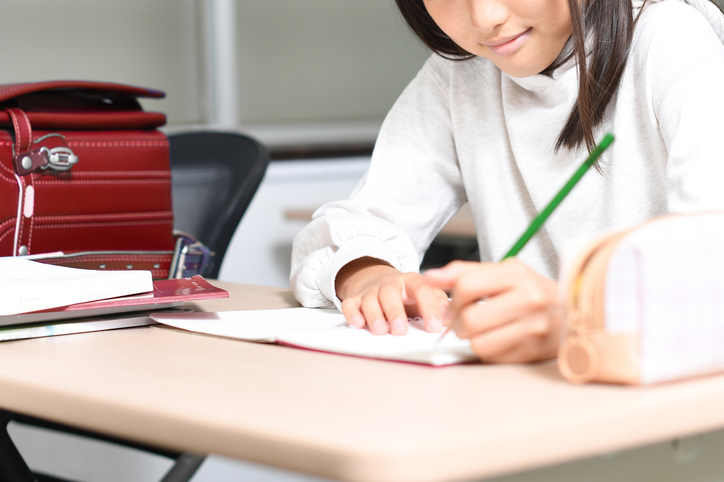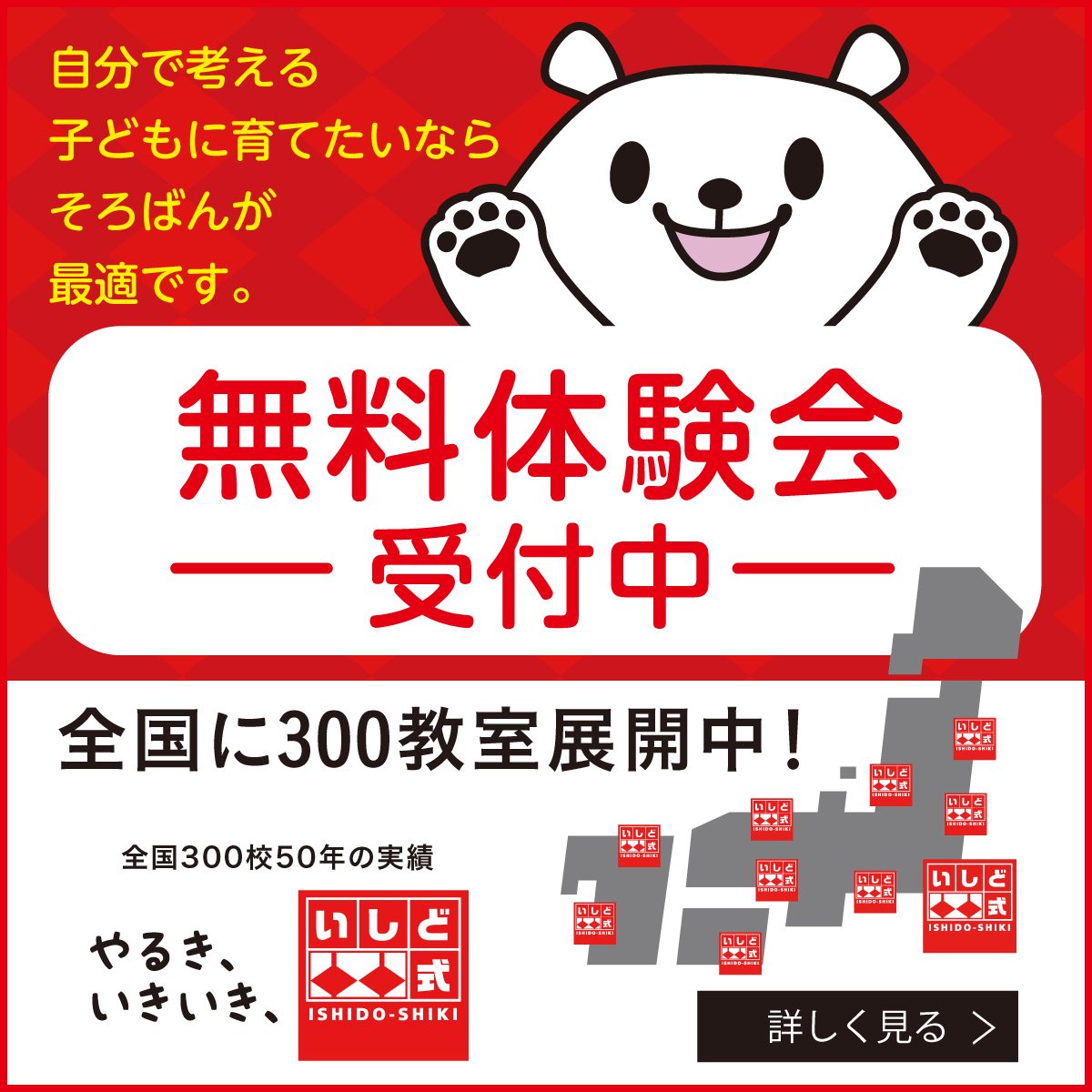教育現場でたびたび聞かれる「ゆとり教育」と「詰め込み教育」という2つの言葉。どちらも子どもの能力を伸ばすのに有用な方法ですが、違いはどこにあるのでしょうか。また、どちらがよいといえるのでしょうか。

- ゆとり教育という方針が打ち出されたのは、2002年施行の学習指導要領です。
この教育を受けた世代は「ゆとり世代」ともいわれています。
それまでの教育はいかによい大学に入る学力をつけるかに重点が置かれる、いわゆる「詰め込み教育」でした。これに対し、ゆとり教育の目的は自ら考える力をつけること。ただ勉強に追われるのではなく、ゆとりのある時間の中でさまざまな経験をして生きる力を身につけてほしいという願いが込められていました。
具体的には、次のようなことが変更されています。
・土曜休みの週休5日制
・総合的学習(教科にしばられない授業)の時間が増加
・円周率は3.14を使うが、およその数で使う場合は3とする
・台形の面積公式は使わず、三角形を使って解く
・中学英語の学習単語数を100減らして900とする
ゆとり教育のメリット
ゆとり教育のメリットとしては以下のことが挙げられます。
・休みが増えて習い事など好きなことに時間が使える
・基本的な学習に集中できる
・ゆっくり考える時間ができる
ゆとり教育のメリットは、子どもたちに学習と生活のバランスをもたらす点にあります。まず、休みが増えることで、習い事やスポーツ、趣味といった好きな活動に取り組む時間を確保でき、個性や才能を伸ばす機会が広がります。
また、授業内容が絞られることで、基本的な学習に集中できるようになり、基礎力の定着がしやすくなります。さらに、授業や課題に追われすぎず、ゆっくり考える余裕が生まれることで、主体的に学び、深く理解する姿勢を育むことができます。
ゆとり教育のデメリット
ゆとり教育のデメリットとして以下の事が挙げられています。
・遊ぶ時間が増えるだけで、時間を有効に使えるとは限らない
・暗記など学習能力を磨く機会が少なくなる
・管理能力を鍛えにくい
ゆとり教育のデメリットは、自由に使える時間が増える一方で、その時間を必ずしも有効に活用できるとは限らない点にあります。さらに、暗記など学習能力を磨く機会が減少することで、基礎的な力の習得に不安が残る可能性があります。
加えて、計画的に学習を進めたり時間を管理したりする能力を身につけにくいことも課題として挙げられます。
詰め込み教育とは?そのメリットとデメリット

詰め込み教育とは、知識を頭に詰め込むことに重点を置いた教育です。日本では長らく詰め込み教育がメインで、受験競争などを激化させてきました。
詰め込み教育のメリット
詰め込み教育のメリットとして、主に以下のことが挙げられます。
・暗記し知識を蓄えることで、さまざまな判断ができる素地を作れる
・歴史や語学など暗記が基礎学力をつける科目もある
・反復するという学習に必要な能力を磨くことができる
詰め込み教育には批判的な見方もありますが、実は基礎的な学力形成において重要な役割を果たしています。小学校や中学校での基礎教育において、必要な情報を確実に記憶することは、その後の応用的な学習の土台となります。
特に、暗記を重視した教育内容の実施は、単なる知識の蓄積にとどまりません。反復学習を通じて集中力や忍耐力が養われ、これらは将来的に複雑な問題に取り組む際の重要な能力となります。また、基礎知識がしっかりと定着していることで、新しい情報を関連づけて理解する力や、批判的に物事を判断する能力の育成にもつながります。
近年の教育改革では思考力重視の傾向がありますが、暗記による基礎固めの重要性を見直し、バランスの取れた教育方法の導入が求められているのです。
詰め込み教育のデメリット
一方で詰め込み教育のデメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
・知識の有無で成績が決まってしまう
・暗記が中心なので飽きやすく、勉強に対するモチベーションが維持しにくい
・覚えたことの応用がききにくい
詰め込み教育のデメリットとして、まず知識量の差がそのまま成績に直結してしまう問題があります。小学校や中学校において、暗記中心の教育内容を実施すると、創造性や思考力よりも単純な記憶力が重視される傾向が強まります。
また、反復的な暗記学習は単調で、生徒の学習意欲の維持が困難になりがちです。特に、膨大な情報を機械的に覚えることが目的化してしまうと、学ぶことの本質的な楽しさや意義を見失い、学習への興味が削減されてしまいます。
さらに深刻なのは、暗記した知識を実際の場面で活用する能力の育成が不十分になることです。テストでは高得点を取れても、現実の問題解決や新しい状況への対応力が身につきにくいという課題があります。このような背景から、近年では思考力や判断力を養う教育の導入が進められているのです。
「ゆとり教育」と「詰め込み教育」どっちがよい?
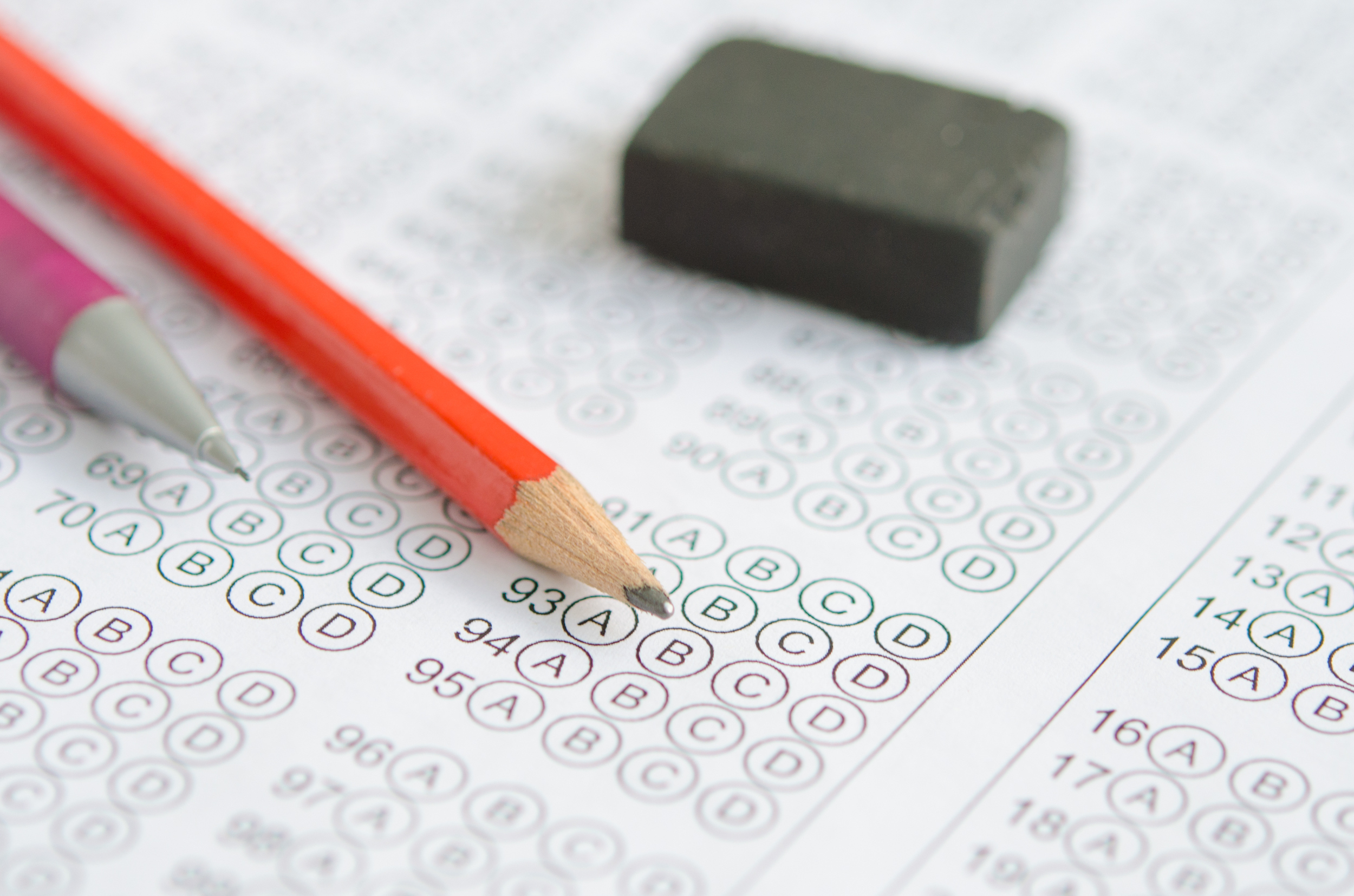
PISAから見た優位性
2002年にゆとり教育が行われた後、PISA(国際学力テスト)の順位が下がったことをきっかけに、ゆとり教育が批判されました。これを受けて、文部科学省は2008年に新学習指導要領を作成、「脱・ゆとり」へと方向転換します。結果、2012年の調査では順位が再び上がります(数学的リテラシー:9位→7位、読解力:8位→4位、科学的リテラシー:5位→4位)。これに対しては、脱・ゆとりが功を奏したと評価されています。
社会へ出て生きていける力が大事
自分で目標を決め、計画を立て、周りの協力を得ながら問題解決していき、ゴールにたどり着く。
そんなふうに自立した子どもを作るのが教育の本質で、それができるならどちらの方法でもよいのではないかと思います。
ゆとり教育については否定的な意見が多いですが、目指した方向性は間違っていなかったと思います。ただ、教育現場に混乱もあり、思ったような活用ができなかったのではないでしょうか。
PISAの結果だけで脱・ゆとりという方向性になってしまったのは残念なことです。
まとめ

どちらにも良い点、悪い点があり、善し悪しは一概には判断できません。いずれにせよ、ゆとり教育が目指したゴールは正当なもので、改めて教育の本質を考えるきっかけになったといえます。
そしてそれは、そろばんなどの習い事でも十分に実現できます。教育の機会は学校の外にもたくさんありますから、真のゆとり教育を行えるところを探してみてはいかがでしょうか。